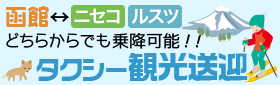■『iso9001品質マネジメント』から『運輸安全マネジメント』
当社では平成17年3月に北海道のタクシー業界で初めて、『ISO9001:品質マネジメントシステム』を認証取得いたしました。
この取組みの目的は、企業のコンプライアンスが強く求められている昨今において、私たち「旅客運送事業者」にとって最も優先すべき使命である『輸送の安全性の確保』について、出来る限りの体制を構築することにありました。
この『ISO9001』を認証取得した後、平成17年・18年・19年とお陰様で、順調にサーベランス(第三者評価機関による定期審査)を終了し、現在に至っております。
一方、私たち運輸業界の監督官庁である国土交通省では、平成18年10月に、『運輸安全マネジメントの導入』が発表され、各事業者が今後、これを必ず取組まなければならない目標とされました。
この『運輸安全マネジメント』の内容は、PDCAサイクル(計画・実施・監視・改善)の継続的な推進により、輸送の安全性を向上させるなど、まさに『ISO9001』の内容と共通するものです。
そこで当社といたしましては、これまで『ISO9001』で取組んで参りました安全性向上の継続的な取り組みを、今後は『運輸安全マネジメントの導入』を通じて、さらに充実した内容にしてゆきたいと考えております。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 令和3年1月1日
令和3年1月1日
函館タクシー株式会社
代表取締役 岩塚晃一
■『運輸安全マネジメント』導入内容について
国土交通省『運輸安全マネジメント』の位置付けによれば、当社は「準大規模事業者」に該当しますので、輸送の安全性を向上させるため、下記の取組みに努めます。
1-1 経営トップの責務
事業者は経営トップの責務を定める。当該責務には、以下の内容が含まれることとする。
- 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有すること。
- 経営トップは、輸送の安全を確保するために必要な予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。
- PDCAサイクルにより継続的に輸送の安全性の向上を図ること等経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行うこと。
1-2 社内組織
事業者は、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築する。体制の構築に当たっては、以下の内容が含まれることとする。
- 運行管理者、整備管理者等を選任すること。
- 安全マネジメントを担当する要員等輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統を決定し、その組織図を作成すること。 (重大な事故、災害等に備え、必要に応じ、予め定めた責任及び権限を超えて、適切かつ柔軟に必要な措置を講じることができるように、その責任者、責任及び権限、並びにそれらを踏まえた指揮命令系統を明らかにしておくこと。)
- 運転者等社員は、1.に定める者等の指示を受けるほか、常に安全の向上に資する技能等の向上を図り、安全な運行等輸送の安全の確保を行うこと。
- (注)
- なお、経営トップ等からの上意下達による指示だけではなく、運転者等現場の声を踏まえ、運転者等社員が参加意識を持って守るべき「社内ルール」を作ることに努めるとともに服務規程等にもその旨を反映させるものとする。
2-1 輸送の安全に関する基本的な方針
事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針を設定し、内部に周知する。当該方針には、以下の内容が含まれることとする。
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
- 安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。
- 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表する。
2-2 輸送の安全を確保するための重点施策
事業者は、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築する。体制の構築に当たっては、以下の内容が含まれることとする。
- 事業者の輸送の安全に関する方針に基づき実施すべき重点施策には、以下の内容が含まれることとする。なお、運行管理者、運転者、車両及び施設等に関する施策については、関係法令等、別に定めるところによるものとする。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令等に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全の確保に関する教育及び研修の具体的な計画を作成し、これを適確に実施すること。
- 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わないこととする。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するように努める。
2-3 輸送の安全に関する目標の設定
事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、事業者が達成したい成果として、目標を設定するものとする。例えば、以下のような指標を用いて目標を設定する。
- 事故件数
- 輸送の安全の確保に関する投資額
- (注)
- 具体的な目標の設定に当たっては、以下の点に留意する。
- 目標年次を設定すること。
- 抽象的目標ではなく、数字の設定等具体的目標とし、外部の者も容易に確認し、事後的に検証できるものとすること。
運転者等現場の声を汲み上げる等、現状を踏まえた改善効果の高いものとすること。 - 社員がイメージし易く、輸送の安全性の向上に対する意識の向上に資するものとすること。
- 目標達成後においては、より高い目標を設定すること。
2-4 輸送の安全に関する計画の作成
事業者は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、また、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
- (注)
- 計画においては、例えば、運転者に対する安全に関する教育の実施、ドライブレコーダー等安全性に配慮した車両等の導入、安全管理委員会の開催、輸送の安全推進に係る行事等できるだけ具体的に記載する。
3-1 安全マネジメント等輸送の安全に関する重点施策の実施
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
3-2 輸送の安全に関する費用支出及び投資
事業者は、輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行う。その際、自社の人材、車両、施設等の実態を把握し、事故やヒヤリハット情報等を十分に分析の上、輸送の安全対策が効果的に行われるよう、重点的に費用支出及び投資を行う。
3-3 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
事業者は、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築する。体制の構築に当たっては、以下の内容が含まれることとする。
- 事業者は、輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関して、経営トップと現場の代表による意見交換、経営トップによる営業所への訪問又は運転者等による営業所内における意見交換等により双方向の意思疎通を十分に行い、適時適切に社内において伝達させ、共有させる。
- 事業者は、経営トップに直結する伝達ルートの確保又は伝達した者に対してマイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合に、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることができるようにするものとする。
3-4 事故、災害等に関する報告連絡体制
事業者は、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築する。体制の構築に当たっては、以下の内容が含まれることとする。
- 事業者は、事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制を整備し、日時、天候、発生場所、事故の種類、事故原因、事故当時の状況等事故、災害等に関する報告が速やかに社内において伝達されるものとする。報告連絡体制の整備等に当たっては、以下の点に留意するものとする。
- 事故、災害等が発生した場合に迅速に対応するため、事故、災害等の当事者が直ちに報告するとともに、社員のいずれかが第一報を受け、速やかに経営トップ又は社内の必要な部局等に伝達しうるような体制とすること。
- 社内において報告連絡体制の周知を図り、社員が報告連絡体制を熟知することにより、事故、災害等が発生した後の対応を円滑に進めること。
- 事業者は、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
3-5 輸送の安全に関する教育及び研修
事業者は、安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、着実に実施する。なお、育及び研修の実施に当たっては、共用の教育・研修施設を活用することも検討する。
- 安全マネジメントが効果的に運用されるよう、安全マネジメントを担当する要員に対する教育及び研修を行う。
- 教育及び研修については、輸送の安全を確保する観点から一層重要な意義を有してきていることから、運転者等の年齢、経歴、能力等に応じたものとする。
4 内部監査・業務の改善に関する事項
- 事業者は、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
- 事業者は、内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 事業者は、悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合においては、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
5-1 情報公開
事業者は、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築する。体制の構築に当たっては、以下の内容が含まれることとする。
- 事業者は、iからiiiに掲げる輸送の安全に関する情報について、ホームページへの掲載等により、毎年度、外部に対し公表するものとする。なお、ivからixの情報ついても、外部に公表するよう努めるものとする。
- 輸送の安全に関する基本的な方針 [令和6年はこちら]
- 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 [令和5年実績はこちら]
- 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故件数) [令和5年実績はこちら]
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 [令和6年はこちら]
- 輸送の安全に関する重点施策 [令和6年はこちら]
- 輸送の安全に関する計画
- 事故、災害等に関する報告連絡体制 [重大事故令和6年はこちら][災害テロ令和6年はこちら]
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
- 安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
- 事業者は、事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
5-2 輸送の安全に関する記録の管理等
事業者は、輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策、報告連絡体制、事故、災害等の報告、輸送の安全に関する内部監査結果その他の安全に関する情報の記録及び保存の方法を定め、保存する。
以上